| 正面登山道 ~ 由布岳(1583.3m) ~ 西登山道 |
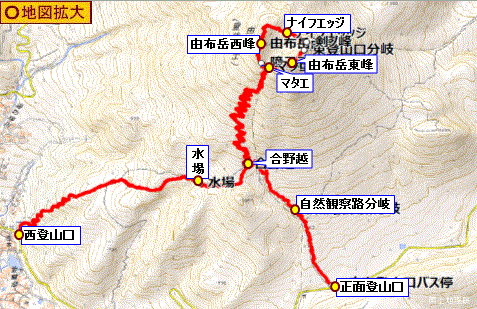
|
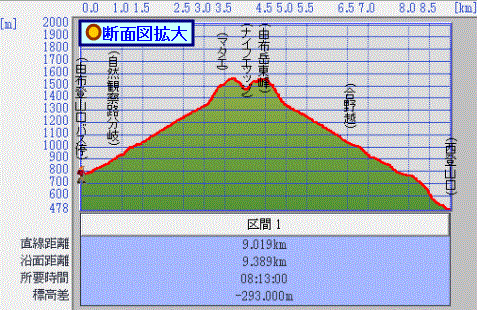
|
| ↑「地図」上の○印をクリックするとその位置の画像を表示します。 | |
| 正面登山道 ~ 由布岳(1583.3m) ~ 西登山道 |
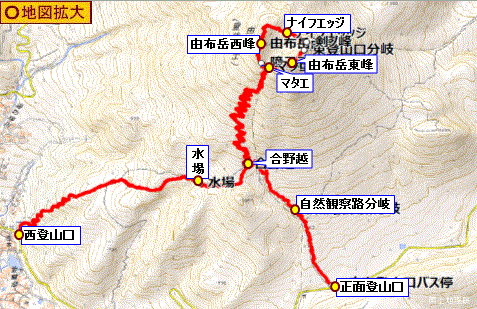
|
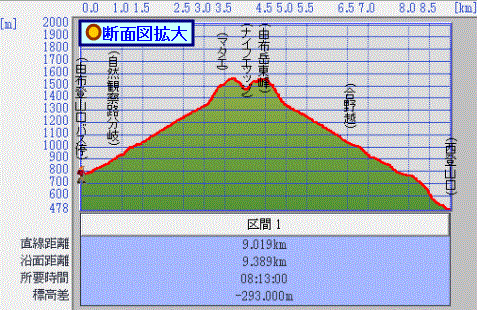
|
| ↑「地図」上の○印をクリックするとその位置の画像を表示します。 | |
| 2015年 5月26日 (火曜日)快晴 メンバー:6名 |
|---|
| 歩行距離 9.4㎞/歩行時間 7時間10分 (休憩時間 1時間09分) 所要時間 8時間19分 |
|---|
|
《レポート画像》 ↓クリックで画像が拡大します。 |
到着 - 出発 | 《ルートポイントのあらまし》 |
|---|---|---|

|
09:57 |
【プロローグ】 昨年出かけた開聞岳で私自身が途中退却を余儀なくされた悔しい気持ちを曳きずったまま、今年の由布岳遠征となったので「今年こそは!」の思いで集合場所の大阪空港に着いて早々とチェックインの準備を済ませるが、オーナーのノムさんをはじめ他のメンバーも既にスタンバイが完了していてその意気込みが伝わってきそうだ。 |

|
10:10 | やがて定刻の15分前に搭乗手続きが始まるが小型のプロペラ機(DHC-8Q400 定員74名)ということで乗客も少なく、すんなりと機内の人になる事が出来た。 |

|
10:17 |
ほぼ満席の乗客が座席に落ち着くと程なくエンジン音も上がって定刻には静かに滑走路から離れ、一気に2万フィート(約6,100m)の飛行高度に達してノンビリとした空中散歩に誘ってくれる。 余談だが、最近は従前のプロペラ機離れから徐々に人気が戻って来たようで、高度が低いために地上の風景を手に取るように眺めることが出来るためだとか・・・・いわば、鉄道の旅においてSLに人気が集まるのに似通っているのかも知れない。 |

|
13:31 |
気流にも幸いして予定時間を10分近く短縮して大分空港に到着したので、次の空港バスを待つ間を利用して昼食を済ませ12時45分発のバスで前泊地の湯布院温泉に向かう。 湯布院温泉が近づくと大分自動車道から明日登ることになっている由布岳が意外に優しい山容を見せてくれる。 |

|
13:50 |
やがて湯布院ICで自動車道を離れたバスが、予定通り終点の由布院駅前バスセンターに着いたところで乗客は吐き出される。 ひとまず今夜の宿に向かうが、チェックインまでには1時間以上もあるので荷物を預かって貰って駅前まで出かけてみる事にする。 |

|
14:10 | 今日2度目となる駅前だが予想していた程の人混みはなく、見かける人の5人に3人は韓国系の旅行者のようでこの辺りが他のエリアと大きく異なっているところだが、関釜フェリーが運行されている事で中国系ではなく韓国系の旅行者が圧倒的に多い事も納得出来る。 |

|
14:14 | 観光スポットも少ないようなので駅前で待機している観光辻馬車にでも乗ってノンビリ巡ろうかと、ケンさんとダオイエさんが案内所に出向くがナント16時までは予約で一杯との事なので馬車を諦める。 |

|
14:29 |
それでは・・・・と言うことで大分川沿いに北東方向に辿って金鱗湖にでも言ってみようと川沿いを進む。 正面には明日訪れる予定の由布岳がドッシリとした双耳の姿を見せている。 明日もあの姿を見せてくれると嬉しいのだが・・・・ |

|
14:55 | 川沿いの道に人通りが増えてくると韓国語が飛び交うようになり、10数台の観光バスが止められている駐車場に着くと「ひょっとして、ココは韓国?」と思う程日本語も聞こえてこない異空間に驚きながら、道を伝うと湖底から温泉が湧くと言われる金鱗湖が姿を現すが、この時間では湯気で靄った湖面を見ることは出来ないそうだ。 |

|
18:08 |
適当に腹ごなしも出来て由布の街並みを垣間見た後は、温泉でユックリ足を伸ばして明日への作戦会議で締めくくった。 今回はノムさんの活躍でフリープランのツアーとなったが、宿の対応も申し分なく私の評価では☆☆☆☆としておこう。 |

|
08:10 |
【催行当日】 朝7時から朝食バイキングで腹ごしらえを済ませて宿をスターとする。 駅前バス停までの途中でコンビニに立ち寄って昼食弁当と飲料水を確保した後、 駅前バスセンター発7時55分の亀の井バス別府湯布院線・別府行きに乗って凡そ15分由布登山口(Ca.770m)バス停で下車する。 この辺り一帯は城島高原に続く高原地帯なので気温も24℃の快適さで登山者を迎えてくれる。 空は快晴で風は微風 |

|
08:12 |
バス停横の広い駐車場には既に大型バスが止まっていて、登山口方向から賑やかな歓声が聞こえてくる。 我々も由布岳を背景に記念写真をと考えているとツアーバスの運転手さんが「シャッターを押しましょうか?」と仰って戴き早速青空に映える最初の一枚に治まることになる。 |

|
08:14 | 前方の歓声も少し遠のいたところで車道を50m程西へ伝うと立派な標識の建てられた由布岳登山口が迎えてくれるので、改めて由布岳の雄姿を切り取って記念となる第一歩を踏み出す。 |

|
08:20 | 何処までも続くような見事な青空が拡がっているが、日陰も少なそうな山なので気温の上昇と直射日光を考えると昨年の開聞岳が想い出されて思わず「ひょっとしたら・・・」の不安が頭を擡げてくる。 |

|
08:35 - 08:39 | やがてスタートして20分程で樹林の中の小さな小径日向岳自然観察路が右に別れるところで、最初の休憩を挟む。 |

|
08:52 | その後も緩やかな山腹沿いを伝うユリ道を捲き登ることになるが、手入れの行き届いた登山道は殆ど露岩も目立たず足の運びもスムーズに高度を上げて行くことになる。 |

|
09:05 - 09:11 |
程なく前方から先行されているツアー客の賑やかな声が近づくと合野越(ごうやごし)(1,020m)に到着するので、休憩を挟みながら少し先行パーティーとの間隔を空ける事とする。 ここから見上げる飯盛ヶ城は綺麗な富士山形の円錐形を見せているが、草原状の山で山頂までの登りも山頂も全く日陰が見あたらないので、夏のシーズンにはなるべく登りたくない山だ。 |

|
09:31 |
合野越を後にすると勾配も強くなって徐々に樹林帯から草原状の急斜面に変わってくる。 日陰の全くなさそうな山頂でもバテないよう小刻みに水分と休憩を挟む事に気を配って、合野越から20分程で樹林を抜け切る手前でひとまず水分補給を兼ねて休憩を採るが、ここまで登ると今まで上に見えていた飯盛ヶ城が眼下に見えてくる。 |

|
10:11 |
さらに40分もジグザグに刻まれた道を伝うと、殆ど直登気味の山道に変わる。 この辺りが1,350m地点でこの先ますます斜度の増す山肌を直登するとはどのような魂胆だろうと、少し首を傾げてしまう。 眼下には湯布院の街並みが静かな佇ずまいをみせているが、実際の街並みと手元の地図を重ね合わせて見ても昨晩の宿がどこにあるのか同定出来そうにないので諦める。 |

|
10:43 | 山頂に目を移すとすぐ手の届く距離に見えるが、予定より僅か10分程度の遅れなので慌てる必要もないと判断してCa.1,480mからの眺望を楽しみながら西峰と東峰の分岐となるマタエに足を運び上げる。 |

|
10:44 - 10:48 | そしてひと登りでマタエ(1,490m)に登り着くと眺望もガラリと変わって、お鉢と呼ばれる噴火口跡に迎えられるが、この山も活火山として扱われていて一瞬引きそうになる。 しかし最も最近でも2,000年前の噴火が最後と案内されているので特に神経質になる必要もなさそうだ。 |

|
10:48 | ここからは左に見える西峰と右に見える東峰、そして正面の鞍部状に見えるナイフエッジを一周するお鉢巡りを楽しむこととするが、ここまで快調に登ってきたトッさんから「少し足に違和感を覚えるのでお鉢巡りはパス」との申し出があったので残念ながら留守番をお願いして、ひとまず西峰から時計回りで辿ってみる事にする。 |

|
10:48 |
まず最初は障子戸(Ca.1530m)と呼ばれる岩壁登りからのスタートとなるが、先行の女性が立ち往生されているので暫く様子を窺う事になる。 やがて登る事を断念されたようで左の岩場に待避されるのを待ってクサリの付けられた岩壁に取り付く。 |

|
10:51 | 先頭は相変わらず快調な足取りのケンさんで、Ca.1,510mにある小さな岩棚まで一気によじ登ったところで |

|
10:52 | 余裕の面持ちで後続メンバーを見下ろしながらまず1枚。 |

|
10:53 | 二番手のダオイエさん、三番手のヒゲさんに続いて高いところが苦手だというノムさんも岩壁を無事に伝い上がる。 |

|
10:56 | クサリ場の登りが一旦途切れるとどこにでもあるような岩尾根を辿ることになるが |

|
10:56 | 振り返ると足下のマタエを挟んで後方に突き上げる東峰の尖峰が目に入る。 東峰はお鉢巡りの仕上げとして踏む予定になっているので、今はチラッと眺めるだけでまずは最初の難所である障子戸のクリアに専念する。 |

|
10:57 | 一旦平坦になった岩尾根を進むとZ字状に見える2段目のクサリ場が目の前に現れるので、まず岩場大好きを自認するケンさんが取り付いて |

|
10:59 | 小広い岩棚まで伝ったところに足場を確保してから、後続メンバーが登るのを待ちながらカメラを向けている。 |

|
10:59 | 最後尾の私が岩棚に着くと、留守番をお願いしたトッさんがマタエからエールを送ってくれている。 |

|
11:00 | 上を見上げると、先鋒のケンさんが余裕の表情で岩場から顔を覗かせている小さな花に挨拶しているるようだ。 |

|
11:03 | 岩場への順番を待っていると、先程西峰への取付を躊躇しておられたペアが登り着かれたので、少し待機をお願いする間に障子戸登りの途中からマタエと東峰方向を小さく切り取ってみる。 |

|
11:06 | いよいよ西峰への核心部といえる障子戸の岩壁をトラバース気味に伝って |

|
11:08 | 岩尾根の南側にあるテラスに渡り着けばひとまず難所は終わる。 |

|
11:08 | 2番手のダオイエさんに続いて岩場が苦手な3番手のノムさんも何とかテラスに辿り着く。 |

|
11:13 | 狭い岩溝を擦り抜けると障子戸は終わって、後は山頂への緩い登りが待っているだけだ。 |

|
11:14 |
山頂が目前に見え出すと最後のチョットした岩場が迎えてくれる。 山頂部の平坦地に登り着いたところで振り返ってみると、恐竜の背を連想させるような障子戸の岩尾根が印象的だ。 |

|
11:17 - 11:28 |
マタエを出て凡そ25分で一等三角点(点名:由布山 標高:1583.2m)が打たれた由布岳西峰を踏むことになるが、標準タイムでは15~20分となっているので少し遊びすぎたのかも・・・・f(^_^;) 何にしても昨年の二の舞は避けることが出来、さらに快晴に恵まれてのリベンジ成功は最高の気分だ。 |

|
11:37 |
さてここからが思案処で、途中にエスケープルートはないので東峰まで周回するか、今登ってきた道を引き返すかを二者択一する事になる。 クサリ場が苦手なオーナーのノムさんの「同じ道を戻るのはイヤ!」という一言で全員お鉢巡りルートを辿ることに決める。 山頂から北方向に辿ると見事なピンクが見えるが、道はここから右手方向への急坂を下ることになる。 ※因みにこの花はミヤマキリシマだと後程教えて戴く。 |

|
11:54 | グングン高度を下げて最低鞍部状に着くと東峰をめがけて登り返すことになり、こちらにも恐竜の背を思わせる幅の狭い岩尾根を上り下りする事になるが、「戻らない」と宣言したノムさんにとっては進むも地獄、戻るも地獄の心境かも知れない。 |

|
11:59 |
先程の障子戸に続いてお鉢巡りの最難関、ナイフエッジが待ち構えているのでノムさんにとっては正念場だと思うが、さすがオーナーの気迫はこの難所も少々の余裕を持ってクリアする事になる。 圧巻はほぼ垂直な4m程の柱状の岩だが、さんざん思案を重ねた末クラックに手がかりを見つけて無事クリアだ。 |

|
12:01 | 次は尖った岩を回り込んで再び鞍部状へ下る事になるので |

|
12:06 | 足場に気をつけて慎重にに伝い下る。 |

|
12:07 | ここでも先鋒のケンさんは一足早く着地して後続メンバーをパチリ!。 |

|
12:07 | 最後尾の私も待ち時間を利用して3番手のヒゲさん、4番手のダオイエさんの足運びを軽くチェックしてみる。 |

|
12:08 | 岩場を下るダオイエさんが気になるのかケンさんもカメラを通してチェックしているようだ。 |

|
12:22 |
楽しいナイフエッジの通過に20分も掛かってしまった事は意外だったが、覚悟していた暑さもほとんど感じなかったのでバテることがなかったのは嬉しい誤算だったと言える。 ※画像は通過後のナイフエッジを振り返ったところ |

|
12:23 | ここからはひたすら東峰への登り返しが始まるのだが、手足を使って所謂三点確保での登りがメインなので足の疲れが分散されて楽しい岩登りが迎えてくれる。 |

|
12:25 | 険しい岩登りが待ち構えているが、一般ルートではないためクサリやハシゴの助けがないので自力で確実に身体を運び上げることになる。 |

|
12:30 - 12:32 | 最低鞍部となるナイフエッジ手前から凡そ25分程で、東峰の尾根続きとなる剣ノ峰(1,550m)に登り着いたところで少し休憩を挟む。 |

|
12:32 | 剣ノ峰からは一旦南へ10m程下ることになり、 |

|
12:34 | 改めてコースを遮る10m程の巨岩を乗り越える事になるが |

|
12:35 | 正面に東峰が見え出すと手前に牙のような形をした鋭い岩峰が進路を妨げる。 |

|
12:36 | コースはこの岩を捲いて乗り越すことになるが、ダオイエさんは乗り越しに四苦八苦して何とか巻き上がる。 |

|
12:37 | 最後を歩く私はメンバーと少し違ったルートを採ったため意外にスンナリと巻き上がる。 |

|
12:41 | この巨岩を過ぎると30m程平坦な尾根道を伝うと、日向越(東登山口)への分岐が左手に岐れるのを見やる。 |

|
12:44 | 目の前にはお鉢巡りの最後となる東峰が鋭い尖峰を突き上げているが、凡そ10分で登り切れそうなのでマタエで待機している筈のトッさんに電話してみる。 しかし電波の加減かどうも繋がりそうにないので諦める。 |

|
12:47 | 東峰への最後の登りは背丈程の雑木に挟まれた薄い踏み跡を伝うようだが、 |
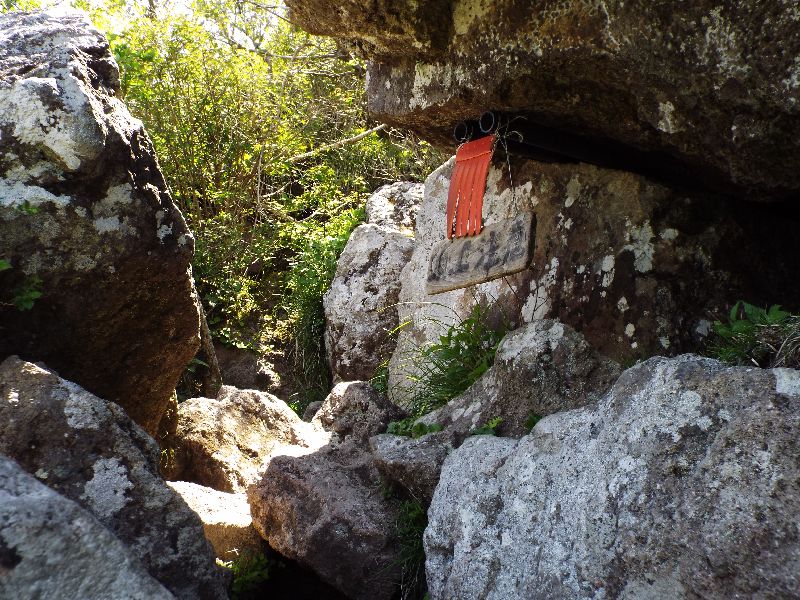
|
12:49 | 東峰直下で噴火口の名残を残して積み重なるように散らばる岩礫に、頭を打たないよう気をつけて狭い隙間を潜り抜ける。 |

|
12:50 - 13:16 |
西峰をスタートして凡そ90分でお鉢巡りルートを伝って東峰(1,580m)まで行き着いたことになる。 この後は下るだけなので、山頂からの絶景をオカズに遅い昼食タイムとするが、マタエで待機中のトッさんも食事は済ませているのだろうと思うが、電話が繋がらないのでは確かめようがない。 |

|
13:17 | 昨年の開聞岳で無念の涙をのむ結果となったが、今回は何とか雪辱出来たので感慨は一入(ひとしお)だ。 |

|
13:17 | 頭上から差し込む直射日光が少し暑いので、他のメンバーから離れて私だけ狭い岩陰で一人っきりの贅沢な時間を寛ぐ事にする。 |

|
13:17 | ジックリ1時間30分も掛けて一回りしてきたお鉢巡りを改めて見回して見ると、火口部の北側に一際低くなったあたりに鋸歯のように鋭く切り立った岩場が目に着くが先程通過してきたナイフエッジだ。 |

|
13:27 - 13:33 | 山頂からの眺望を充分楽しんだ後は、トッさんの待っているマタエに下るのだけなので、もう一度東峰の姿を目に焼き付けて見る。 |

|
14:37 | 2時間40分程で無事2度目となるマタエに下り着いたところで留守居役のトッさんと合流して、登路に歩いた正面登山口への道を下ることになるが、浮き石が結構目立つので乗り上げないよう登り以上に気をつけて足を運び降ろす。 |

|
14:51 - 14:55 |
ノンビリと1時間20分掛けて下ると、樹林帯の途切れるところで合野越に飛び出す。 往路では何気に足を休めたのだが、上部から見ると正面登山口へのルートの右(=西)側に細い踏み跡が伸びて美しいコニーデ状の山容を見せる飯盛ヶ城への取付と西登山口への分岐になっているのでこの道に足を進める。 |

|
15:00 |
4~5分で飯盛ヶ城(1,067m)登り口に着く。 予定ではここから飯盛ヶ城をピストンする事なっていたのだが、天候に恵まれた山頂で十分な絶景を望むことが出来たので立ち寄りを止めて、飯盛ヶ城の北側鞍部に沿ってガレキの敷き詰められたような歩きにくい左足上がりの道を西へ向かう。 |

|
15:12 - 15:18 |
暫くは広々とした草原状を西へ辿るが、分かり難い分岐が右に岐れるところで危惧していたとおり先行メンバーは気が付かずに通過してしまう。 最後尾から分岐を見落としたことを伝えると苦笑いで軌道修正して事なきを得るが、先頭グループのこの癖は何とか改善して欲しいものだ。 |

|
15:18 | 程なく樹林を抜けると目の前に素晴らしい高原風景が拡がると、足の疲れも一瞬吹っ飛んでしまい13年の7月に歩いた蒜山の風景とダブってくるのだが、このときは残念なことに途中撤退を余儀なくされたのだが今回の山歩きでは蒜山・開聞岳でのリタイヤの悔しさを完全に払拭する事が出来た。 |

|
15:22 | 小さく起伏する草原の前方には湯布院の街並みが見えてくる。 |

|
15:22 | 相変わらず頭上に拡がる青空の端に、今下ってきた高原風景から突き上げるように、見事な円錐形の飯盛ヶ城が見送っていてくれる。 |

|
15:27 | そしてその左(=北)側からはドッシリと横たわる双耳の由布岳も見送ってくれるので、何度も振り返ってこの絶景を目に焼き付ける。 |

|
15:38 | 時間が許せば一日中でも寝そべっていたい気持ちに襲われながら草原を進むと、 |

|
15:40 | やがて樹林帯への分岐が右に岐れるので、樹林の道に足を進めることになり |

|
15:48 | 恵まれた展望もここで終わって後はひたすら樹林の中に続く山道を伝い下ることになる。 |

|
16:05 | 樹林帯を辿り出して凡そ20分で前方の樹木が徐々に明るくなると麓にある岳本の集落がチラホラと視界に入りだす。 |

|
16:24 |
快適な道をさらに20分程下ると堰堤の横に下り着いて、西登山口(岳本)の標識が現れる。 道標横には多くの杖が置かれているので、ケンさんもここまでお世話になった杖を立てかけて道路(県道216号)に飛び出す。 |

|
16:29 | 道路の右前方にはお馴染みのコンビニも顔を覗かせ、左方向に200mほど足を運べば金鱗湖が横たわっているが、こちらは昨夕立ち寄ったのでひとまずコンビニで一人一人が自分へのご褒美を求めてプレ反省会で舌鼓を打つ。 |

|
18:13 | この後は20分程掛けて昨夜からの連泊の宿まで足を運んで、充実した反省会で大いに盛り上がった後は次回のノムさん企画を期待して遠征トレックは終了した。 |