| 悙曮帥扟 乣 廫敧挌嶳(878.0m) 乣 廫敧挌旜崻 |
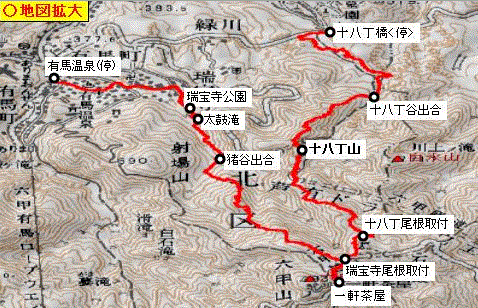
|
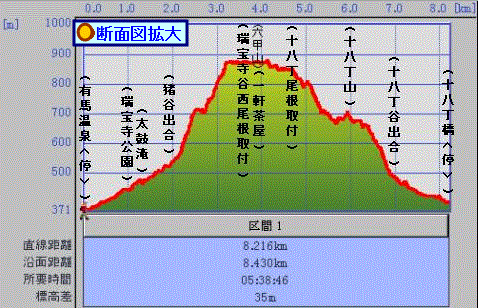
|
| 仾乽抧恾乿忋偺仜報傪僋儕僢僋偡傞偲偦偺埵抲偺夋憸傪昞帵偟傑偡丅 | |
| 悙曮帥扟 乣 廫敧挌嶳(878.0m) 乣 廫敧挌旜崻 |
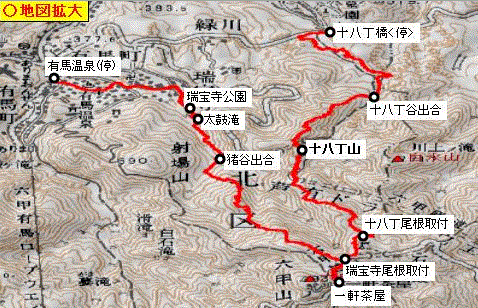
|
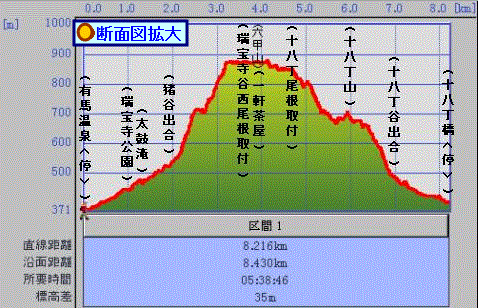
|
| 仾乽抧恾乿忋偺仜報傪僋儕僢僋偡傞偲偦偺埵抲偺夋憸傪昞帵偟傑偡丅 | |
| 俀侽侽俇擭侽俈寧俀俋擔 乮搚梛擔乯惏傟屻堦帪塉 儊儞僶乕丗扨撈 |
|---|
| 曕峴嫍棧丂俉丏俇噏乛曕峴帪娫丂係帪娫俆俇暘 乮媥宔帪娫丂侽帪娫係侽暘乯 強梫帪娫丂俆帪娫俁俇暘 |
|---|
|
乻儗億乕僩夋憸乼 伀僋儕僢僋偱夋憸偑奼戝偟傑偡丅 |
摓拝 - 弌敪 | 乻儖乕僩億僀儞僩偺偁傜傑偟乼 |
|---|---|---|

|
10:26 |
廰懾偱戝暆偵僶僗偑抶傟丄梊掕傛傝25暘抶傟偰桳攏壏愹僶僗掆傪僗僞乕僩偡傞 仸棤榋峛偱傕曑憰摴楬偺徠傝曉偟偼嫮偔丄庤尦偺壏搙寁偼偼32亷傪巜偟偰偄傞偺偱悈暘傕2噂弨旛偟偰惵嬻偺壓傪僲儞價儕曕偒弌偡 |

|
10:27 | 偄偮傕偼塃愜偡傞嬥偺搾傕崱夞偼嬋偑傜偢偵塃庤偵尒傗偭偰恀偭捈偖捠傝夁偓 |

|
10:34 | 惷偐側壏愹奨傪捠傝敳偗傞偲丄傗偑偰悙曮帥扟嵍娸偺僶僗摴偵撍偒摉偨傞偺偱摴側傝偵塃愜偡傞 |

|
10:36 | 偡偖忨幪嫶偑嵍偵尰傟傞偺偱嵍愜偟偰偙偺嫶傪搉傝丄偡偖偺暘婒傪塃偵愜傟偰塃娸増偄傪撿搶偵怢傃傞儌儈僕嶁傪儐僢僋儕扝傞 |

|
10:44 | 愗庤暥壔攷暔娰偲悙曮帥岞墍傪寢傇巐偮捯偱摴昗偵廬偭偰塃愜(=撿曽岦)偟丄摴側傝偵慜曽偺庽椦偵岦偐偭偰恀偭捈偖扝傞偲20m掱恑傫偩偁偨傝偱塃傊偺摴偑暘偐傟傞偺偱偙偙傪傕偆堦搙塃愜偟偰悙曮帥挰岞墍偵拝偔 |

|
10:44 | 偦偟偰悙洀帥嫶偐傜岞墍撪偺嶶嶔楬偵懌傪恑傔 |

|
10:47 | 墍撪偺墱傑偭偨偲偙傠偱廏媑墢(備偐傝)偺擔曢傜偟偺掚偵寎偊傜傟傞 |

|
10:46 | 廏媑偑堦擔拞惔梀傪妝偟傫偩岄斦偲彂偐傟偨埬撪斅傪廬偊偨愇偺岄斦傕愄傪幟偽偣傞傛偆偵惷偐側樔傑偄傪尒偣丄嶳嵺偺戲増偄偵峀偑傞庽椦偩偗偁偭偰愭掱傑偱32亷傪巜偟偰偄偨壏搙寁傕30亷偵壓偑傝彊乆偵夣揔偝偑憹偟偰偔傞傛偆偩 |

|
10:53 | 巄偔岞墍傪弰偭偨屻偼偡偖墶傪棳傟傞悙曮帥扟偺愳娸傊壓偭偰 |

|
11:00 - 11:01 |
堦扷嵍娸傊旘傃愇偱搉傝丄彮偟忋棳偱塃娸傊搉傝曉偡偲棊嵎7乣8m偺懢屰戧偺慜偵拝偔 憗懍椓偟偄晽偲儅僀僫僗僀僆儞偑寎偊偰偔傟傞 |

|
11:00 | 偙偙偐傜戧偺忋棳傊慿傞偵偼嵍庤(=塃娸)偺娾暻偵崗傑傟偨旝偐側娾扞傪崅尀偔埲奜偵側偝偦偆偩偑丄崱夞偼戲曕偒偑栚揑偱偼側偄偺偱20m掱壓棳傊栠偭偰嵍娸増偄偺嶳摴傪扝傞帠偵偡傞 |

|
11:04 | 嵍娸偵拝偗傜傟偨嶳摴偼戧偺偡偖忋棳偱嵍偐傜愇愊傒偺墎掔偵尒憲傜傟偰50噋暆偺娚傗偐側幬柺傪搊偭偰備偔 |

|
11:07 | 嵍懌壓偵棳傟傞悙曮帥扟偺悾壒傪挳偒側偑傜帺慠椦偵埻傑傟偨惷偐側摴傪忋棳曽岦偵揱偆偑 |

|
11:09 | 傗偑偰摴榚偵僒僒尨偑栚偵晅偒偩偡偲丄戧偐傜5暘掱偱嶳娫偺暤埻婥偑昚偭偰偔傞 |

|
11:11 | 傗偑偰嶳摴偼旘傃愇揱偄偱塃娸傊搉傞偙偲偵側傞偺偱丄晜偒愇偵婥傪晅偗偰搉徛偡傞 |

|
11:12 | 嵞傃棳傟傪朌偆傛偆偵嵍娸傊搉傝曉偡偑摴昗側偳偼尒偁偨傜側偄偺偱丄姴傗彫巬偵姫偐傟偨僥乕僾傪廍偄側偑傜惔棳増偄傪扝傞偲 |

|
11:13 | 悢10m偱傑偨傑偨塃娸偵搉傝曉偡 |

|
11:18 | 偙偺屻巄偔偼彫婥枴偺椙偄塃娸偺僒僒偲嶨栘偵嫴傑傟偨暯扲側摴傪扝傞帠偵側傞 |

|
11:21 | 愭掱搉徛偟偨強偐傜10暘嬤偔偱悙曮帥扟偱嵟屻偺搉徛億僀儞僩偑寎偊偰偔傟傞偺偱丄彫巬偵晅偗傜傟偨僥乕僾偺埬撪偱嵍娸傊搉傝 |

|
11:29 | 5暘彮偟偱挅扟弌崌傪嵍偵丄塃庤偵庯偺偁傞愇愊偺墎掔傪尒偰塃枔偵怢傃傞挅扟偺塃娸偵搉傞偑 |

|
11:32 |
椓偟偄戲増偄摴偼偙偙傑偱 偙偙偐傜偼悙曮帥扟偲挅扟偺娫偵撍偒忋偘傞悙曮帥扟惣旜崻偵庢傝晅偒丄慡偔摴昗偺側偄摜傒愓偲僥乕僾偵埬撪偝傟偰丄幩応嶳偵塃庤攚屻偐傜尒庣傜傟偰媫嶁傪忋傞 |

|
11:46 - 11:47 | 揥朷傕側偄媫側旜崻偵庢晅偄偰栺10暘偱Ca.610m偺旜崻怟偵搊傝拝偒丄悂偒弌傞娋傪捔傔側偑傜彮偟屇媧傪惍偊傞 |

|
11:51 |
業娾偺旘傃弌偟偨旜崻傪5暘嬤偔扝傞偲傗傗暯扲側僐僽偵拝偒丄庽栘偺愗傟栚偵偼塃庤屻曽偐傜尒壓傠偡傛偆偵戝傜偐側僪乕儉忬偺幩応嶳偑尒偊傞傛偆偵側傞 杒柺偺孹幬抧側偺偱懢梲偼庽栘偵幷傜傟偰傎偲傫偳捈幩偡傞偙偲偼側偄偺偱丄撿柺偺搊傝傛傝偼辍偐偵弸偝偼姶偠側偄傛偆偩 仸偙偙傑偱棃傞偲婥壏傕28亷偲婔暘椊偓傗偡偔側偭偰偒偨 |

|
12:10 | 旜崻嬝偑彊乆偵崅搙傪忋偘傞偵廬偭偰嵍偵崗傑傟偨悙曮帥扟偼怺偔媫側棊偪崬傒傪尒偣傞偑丄嶳敡傪暍偄恠偔偡嶨栘偵幷傜傟偰墎掔偩傜偗偺扟掙偼尒壓傠偝側偔偰傕椙偄傛偆偩 |

|
12:19 |
慜曽偵憠偣偨僺乕僋偑尰傟傞偲摴偼塃(=惣懁)傪尀偔傛偆偵側傞 偦偺尀偒摴偵傕棊愇愓丠偑捠峴傪朩偘偰偄傞偺偱丄怴偨側棊愇偵拲堄偟偰懌憗偵偙偺応傪捠傝夁偓傞偲 |

|
12:23 | 偡偖惼偄娾夠偑僫僀僼儕僢僕忬偵懕偔偺偱丄妸棊偵婥傪晅偗偰儎僙旜崻傪捠傝敳偗傞 |

|
12:30 | 傗偑偰慳傜側庽椦偵僒僒偑栚棫偭偰偔傞偲 |

|
12:37 | 摴偼愗傝棫偭偨娾旜崻偺塃(=惣)懁傪尀偔傛偆偵揱偄 |

|
12:41 |
僒僒偑峀偑傝偩偟偰10暘掱偱旜崻忋偺暯扲抧偵拝偔 憡曄傢傜偢嵍壓偵怺偔愗傟崬傫偩悙曮帥扟偼尒壓傠偡偙偲偑弌棃側偄偑丄憕偒暘偗偰扝傞僒僒旜崻偺嵍懁偼媫幬柺偵側偭偰偄傞偺偱摜傒愓傪奜偝側偄傛偆偵懌傪恑傔傞 |

|
12:45 | 堦柺偺僒僒尨偑搑愗傟傞偲傓偒弌偟偺栘僲崻偑栚棫偮傛偆偵側傝丄崻偭偙偺旘傃弌偟偨庽娫傪僥乕僾棅傝偵扝傞偲 |

|
12:47 - 12:49 |
傗偑偰Ca.810m抧揰偺栘堿偵拝偔 偙偙傑偱棃傞偲婥壏傕僌儞偲壓偑偭偰24亷傪巜偟偰偄傞偑丄栚偺慜偵嵟屻偺媫搊傝偑懸偪峔偊偰偄傞偺偱彮偟懌傪媥傔偰娋傪捔傔傞帠偵偡傞 |

|
12:58 | 栘偺娫墇偟偵悙曮帥扟尮棳晅嬤偺僂儞僓儕偡傞傎偳偺墎掔偑栚偵拝偒弌偡偲嵍庤偵奒抜偺晅偗傜傟偨岺帠梡曕摴偑尰傟傞偑 |

|
偡偖壓偱恑傔傜傟偰偄傞怴偟偄墎掔偺憿塩岺帠傪尒傗偭偰丄旜崻偺嵟崅抧揰傊懕偔僒僒尨偺娵栘奒抜傪搊傞偲椓偟偘側僸僌儔僔偺柭偒惡偵傕椼傑偝傟傞 | |

|
12:59 | 偡偖岺帠偱愗傝奐偐傟偨尮摢晹傪捠傞帠偵側傞偺偱丄嵍壓偵怺偔愗傟棊偪偨悙曮帥扟偲柍嶴偵嶍傝庢傜傟偨嶳敡丄偦偟偰婔廳偵傕愗傝崗傑傟偨嵒杊墎掔偑寵偱傕栚偵晅偔偺偱彮偟暋嶨側婥暘偵偝偣傜傟傞 |

|
13:04 | 旜崻摴偑傎傏暯扲偵側偭偰偔傞偲戝偒側業娾偑旘傃弌偟偨抧揰傪捠夁偡傞偑丄偙偺曈傝偑抧宍恾忋偺嵟崅抧揰(Ca.875m)偵側傞傛偆偩 |

|
13:10 |
娚傗偐偵壓傝弌偡偲5暘彮乆偱倄帤忬偺暘婒偵弌傞偑梊掕傛傝抶傟偨偺偱抶偄拫怘傪愛傞偙偲偵偡傞 塃偼堦尙拑壆丒嵟崅曯傊丄傑偨嵍偼曮捤丒愇曮揳傊偺儖乕僩偵側傞偺偱庢傝偁偊偢嵍傊扝偭偰怘帠応強傪扵偡帠偵偡傞 |

|
13:12 |
嵍傊恑傒幵摴偵旘傃弌偟偰崱扝偭偰偒偨摴傪怳傝曉偭偰捈嬤偺媥宔億僀儞僩偵巚偄弰傜偣偰偄傞偲丄媫偵椻偊偨價乕儖偑堸傒偨偔側偭偨偺偱堦尙拑壆傊媫偖帠偵側傞 仸嵟弶偐傜偁偺暘婒傪塃偵嵦偭偰偍偗偽傕偆彮偟憗偔價乕儖偵偁傝偮偗傞偺偵偲僠儑僢僺儕斀徣偟側偑傜懌塣傃偼帺慠偵懍偔側傞 |

|
13:17 - 13:31 | 堦尙拑壆偵拝偔偲憗懍椻偨偄價乕儖傪堦婥偵岮偵棳偟崬傒丄帄暉偺堦帪偵怹偭偨屻偼峇偰傞偙偲傕側偄偺偱宨怓傪妝偟傒側偑傜惷偐偵拫怘傪愛傟傞応強傊堏摦偡傞 |

|
13:37 - 13:57 |
嵞傃廲憱楬傪曮捤曽岦偵岦偐偆帠偵側傝丄屻敨姫嶳傪尀偒捠傞媽摴偵懌傪恑傔傞偲慡偔恖捠傝傕搑愨偊傞 偨偩堦偮丄墎掔岺帠梡偺廳婡偝偊柍帇偡傟偽栚偺慜偵奼偑傞戄偟愗傝忬懺偺挱朷傪尒搉偟側偑傜拫怘僞僀儉傪妝偟傔偦偆側偺偱丄偙偙傪拫怘応強偵寛傔傞偑丄摢忋偵奼偑偭偰偒偨廳偄塤偑尒傞尒傞偆偪偵廃埻傪墧怓偺塤偱暍偄恠偔偟偰棃偨偺偱拫怘傕彮偟憗傔偵愗傝忋偘傞偙偲偵側傞 |

|
13:59 |
壓傝巒傔傞慜偵埲慜曕偄偨帠偺偁傞敀悈旜崻傊偺庢晅偒傪妋偐傔偰傒傞偑丄僒僒偑惗偄栁偭偰摜傒愓偡傜尒暘偗傞偙偲偑擄偟偔側偭偰偄傞 偦傟傎偳棙梡偡傞僴僀僇乕偑彮側偄僐乕僗偱偁傞帠傪棤晅偗偰偄傞偺偩傠偆 |

|
14:02 |
惣曽岦傊50m掱栠傞偲柧愇丒恄屗丒曮捤僇乕僽噦108偲彂偐傟偨昗幆偲僇乕僽儈儔乕偺偁傞廫敧挌旜崻傊偺庢晅揰偑偁傞 僈乕僪儗乕儖傪墇偊偰僥乕僾偺晅偗傜傟偨嵶偄摜傒愓偺儎僽摴偵懌傪摜傒擖傟傞偲丄掱側偔墧怓偺嬻偐傜寽擮偟偰偄偨塉棻偑棊偪巒傔傞 |

|
14:04 |
塉偱敄埫偔側偭偨僒僒尨傪憕偒暘偗偰媭偪偐偗偨娵栘奒抜傪壓傞偲娚傗偐側壓傝嶁偵曄傢傞 嬻偼堦憌埫偔丄僪儞儓儕偲偟偨塤娫偐傜崀傞塉偼彮偟戝棻偵側傞偑栘乆偺梩偭傁偑庴偗巭傔偰偔傟傞偺偱捈愙擥傟傞偙偲偼側偝偦偆 傗偑偰暘婒偑尰傟傞偑丄嵍傊偺摴偼儘乕僾偱捠峴巭傔偝傟偰偄傞偺偱偍偦傜偔墎掔岺帠拞偺悙曮帥扟傊壓傞摴偲巚傢傟傞 偙偙偼旜崻揱偄偱塃傊怢傃傞憠偣偨僒僒旜崻傪懌扵傝偱儐僢僋儕偲扝傞帠偵側傞 |

|
14:08 | 娚傗偐偵婲暁偟側偑傜怢傃傞僒僒旜崻偵偼旝偐側摜傒愓偑懕偄偰偄傞偺偱丄拤幚偵偙傟傪扝傝 |

|
14:09 | 堦扷塃(=搶懁)偺廫敧挌扟傊壓傝婥枴偵儘乕僾偺挘傜傟偨塃壓偑傝偺幬柺傪揱偆偲 |

|
14:18 |
摴偼嵞傃旜崻嬝傪扝傞傛偆偵怢傃偰峴偔偑丄儖乕僩偑杒惣曽岦偵僇乕僽偡傞偲劙忬偺暘婒偑尰傟傞 摴昗偼側偄偑偙偙偼僆儗儞僕怓偺僥乕僾偵桿摫偝傟偰塃傊懌傪恑傔偰傒傞 憡曄傢傜偢帇奅偼僈僗偵幷傜傟偰偄傞偑偄偮偺娫偵偐塉偼忋偑偭偨傛偆偱忋嬻傕彊乆偵柧傞偔側偭偰偒偨 |

|
14:20 | 偳偪傜傪嵦偭偰傕摨偠偩偭偨傛偆偱丄彫偝側儎僙旜崻偺僐僽傪塃偐傜尀偔偲偡偖愭掱暘偐傟偨摴偑嵍偺僐僽傪壓偭偰崌棳偡傞 |

|
14:22 |
傗偑偰埰晹偵拝偔偲旜崻摴傪墶愗傞傛偆偵嵶偄摴偑岎嵎偡傞 嵍偼悙曮帥扟偵懕偒丄塃偼廫敧挌扟傊壓傞傛偆偩偑丄偙偙偼僆儗儞僕偺僥乕僾偵廬偭偰捈恑偡傞 |

|
14:25 | 摜傒愓偼椗慄偐傜堩傟偰嵍(=惣懁)傊壓偭偰峴偔偑傗偑偰娚傗偐偵搊偭偰嵞傃椗慄偵弌傞 |

|
14:27 | 偡偖尰傟傞儎僙偨娾旜崻偐傜偼媫岡攝偺墯抧傪嫴傫偱峏偵杒傊偲怢傃偰 |

|
14:31 | 5暘掱偱媫側嵍孹幬偺尀偒摴傪捠夁偡傞偺偱摜傒奜偝側偄傛偆拲堄偟偰摜傒愓傪偨偳傞偲 |

|
14:32 |
撍慠栚偺慜偵媫側壓傝偑懸偪峔偊偰偄傞 宨怓偵尒偲傟偰妸棊偟偨傝栘偺崻偵鏣偐側偄傛偆懌壓偵傕婥傪攝傜側偗傟偽側傜側偄偺偱彮偟怲廳偵壓傞 |

|
14:33 | 塉忋偑傝偺僈僗偱揥朷偼傎偲傫偳棙偐側偄偑塃庤偵僂僢僗儔偲埌桳僪儔僀僽僂僃僀偑巔傪尰偡 |

|
14:38 |
偝傜偵娚傗偐偵壓傞偲僪儔僀僽僂僃僀偺懁摴偵旘傃弌偡 塃庤屻曽傪怳傝曉傞偲億僢僇儕偲岥傪奐偗偨埌桳瑭摴偑彮偟夃傫偱尒偊傞 |

|
14:40 | 懁摴傪15m掱恑傓偲嵞傃嵍傊偺嶳摴偑僥乕僾偵埬撪偝傟偰庽椦偵怢傃傞偺偱嵍傊偺嶳摴傊懌傪恑傔傞 |

|
14:41 |
壏搙寁傪尒傗傞偲尰嵼22亷 儎僙旜崻偵弌傞偲僈僗傕愗傟偰帪愜敄擔偑婄傪擿偐偣偰偔傟傞 |

|
14:47 | 5暘掱偱埰晹偵拝偔偲丄嵍慜曽偐傜愗傝棫偭偨戝娾偺弌寎偊傪庴偗傞偺偱摴偼塃(=搶)懁傪尀偒忋偑傞 |

|
14:50 |
幵摴偐傜10暘偱717m偺僺乕僋偵拝偔偲壗張偐偺僒僀僩偱廫敧挌嶳(717m)偲徯夘偝傟偰偄偨帠傪晄堄偵巚偄晜偐傇偑丄廃埻傪尒搉偟偰傕偦傟傜偟偄嶳柤斅偼尒偁偨傜側偄 嶳捀偼倄帤忬偺暘婒偵側偭偰偄傞偑丄塃偵偼捠峴巭傔偺栘巬偑搉偝傟偰偄傑偡偺偱愒丒惵丒墿丒椢丒僆儗儞僕偲擌傗偐側僥乕僾偑晅偗傜傟偨嵍偺摴傪壓傞 塃傊偺摴偼庤尦偺抧恾偵嵹偭偰偄傞廫敧挌扟傊壓傞揰慄偺摴偺傛偆偩 |

|
14:54 | 埰晹傪夁偓傞偲摴偼壓憪偵暍傢傟偰彮偟摜傒愓偑暘偐傝偵偔偔側偭偰偔傞偑丄旜崻嬝傪尒嬌傔偰拤幚偵懌傪恑傔傞偲 |

|
14:56 | 慜曽偺庽栘偑搑愗傟偰惓柺偵栘偺娫墇偟偺榋峛僇儞僩儕乕僋儔僽偑彮偟枭偭偨巔傪尒偣 |

|
15:04 |
偙偙傑偱壓偭偰偔傞偲偄傛偄傛廫敧挌旜崻怟偐傜廫敧挌扟傊偺媫側壓傝偑巒傑傞 傑偢庤巒傔偵2m掱偺娾応偺壓傝偑懸偪峔偊偰偄傞偺偱丄摜傒奜偝側偄傛偆偵壓傞 |

|
15:06 | 娾応偺師偵懕偔媫嶁偼棫栘傗崻偭巕偺彆偗傪庁傝偰堦曕偢偮廫敧挌扟偵壓傞偑丄栚偺慜偵栧斣偺傛偆側娾旜崻偑棫偪嵡偑偭偰偄傞偺偱塃庤偵晅偗傜傟偨棅傝側偄摜傒愓傪尀偒壓傞 |

|
15:11 |
懕偄偰尰傟傞儎僙旜崻傪揱偆偲傗偑偰旜崻怟偐傜塃庤(=廫敧挌扟)曽岦偺嶨栘傪朌偭偰媫側壓傝偑弌寎偊偰偔傟傞 妸棊偟側偄傛偆偵栘棫偺彆偗傪庁傝側偑傜儐僢僋儕偲懌傪塣傇 |

|
15:31 | 婔暘岡攝偑娚傗偐偵側傞偲3m暆偺椦摴丠偵旘傃弌偡偑丄偙偺摴偑抧恾偵嵹偭偰偄傞廫敧挌扟増偄偺揰慄偺摴偺傛偆偩 |

|
嵍傊恑傓偲偡偖3m暆偺摴偼巔傪徚偟偰嵶偄嶳摴偵栠傞 | |

|
15:33 | 傎傫偺彮偟偱嵞傃3m暆偺峀偄摴偑巔傪尰偡偲偡偖塃墶偵扟愳偺棳傟偑嬤偯偄偰偔傞偺偱丄摴傪奜傟偨嵍娸偐傜廲憱楬偺憱傞悈柍嶳曽岦傪怳傝曉偭偰柍帠偵壓傝拝偄偨帠傪幚姶偡傞 |

|
15:41 |
摴偵栠偭偰偦偺傑傑恑傓偲椦摴偵崀傝棫偭偨偲巚偭偨偺偼僰僇婌傃偩偭偨傛偆偱丄傑偨摴偼嫹偄嶳摴偵媡栠傝偟偰偟傑偭偨傛偆偩 ゥ茖緜杺艃S乕儖傑偱偵偼傑偩彮偟帪娫偑妡偐傝偦偆 |

|
15:48 - 15:53 |
彮偟峳傟偨扟増偄偺摴傪10暘嬤偔恑傓偲塃庤傪捠傞峀偄摴偵崌棳偡傞 塃庤偵偼攑壆偺傛偆側寶暔偑尒偊傞偑傕偪傠傫恖塭偼尒摉偨傜側偄 嵍偐傜偼椻偨偄悈偑棳傟弌偰偄傞偺偱偙偙偱娋傪怈偄偰娙扨側拝懼偊傪嵪傑偡 仸峀偄摴偐傜崱弌偰偒偨抧揰傪怳傝曉偭偰傒傞偲丄乽傂傚偭偲偟偰偙偺峀偄摴偑抧恾偵忔偭偰偄傞揰慄偺摴丠乿偲偺媈栤偑桸偄偰偔傞偑 |

|
15:54 | 偙偙傑偱棃傞偲娫堘偄側偔僑乕儖娫嬤偱偁傞偙偲偑妋怣弌棃傞偺偱丄埨怱偟偰峀偄曑憰摴楬傪僲儞價儕壓偭偰戝偒偔嵍傊嬋偑傞偲惓柺偵僶僗摴偑尒偊傞 |

|
15:55 | 弌岥偵偼尞偺妡偗傜傟偨僎乕僩偑棫偪偼偩偐偭偰偄傞偺偱嵍嬿偐傜幵摴傊敳偗弌偡偑 |

|
15:56 | 旘傃弌偟偨偲偙傠偼桳攏嵵応慜偺僶僗摴側偺偱偙偙傪塃傊岦偐偄 |

|
16:02 |
嵵応慜偐傜5暘偱廫敧挌嫶(敀悈嫭)僶僗掆偵摓拝偟偰丄崱夞傕柍帠偵梊掕僐乕僗傪扝傟偨枮懌姶傪枴傢偆娫傕側偔16:06敪丒曮捤峴偒偺僶僗偑棃偨偺偱丄椻朳偺岠偄偨僶僗偵梙傜傟偰婣戭偺搑偵拝偔 仸崱夞梡堄偟偨2噂偺悈暘傕栺敿暘巆偟偰偺僑乕儖偼丄僐乕僗愝掕傪棤榋峛偵偟偨偙偲偑惓夝偩偭偨傛偆偩 |