| �c�c�W�I�J �` �����R(1125.0m) �` ���J |
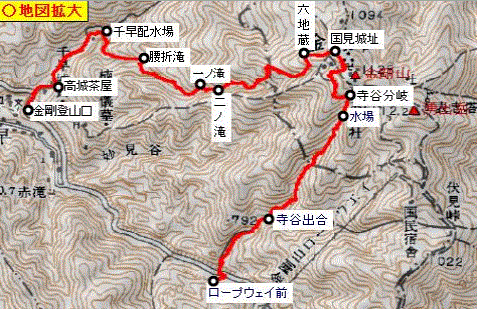
|
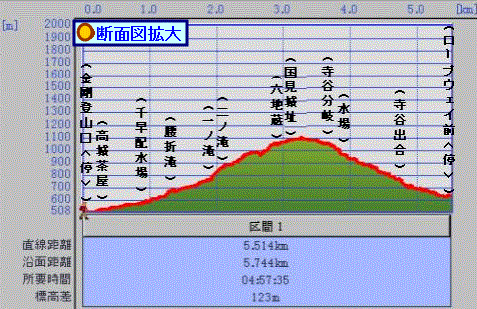
|
| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |
| �c�c�W�I�J �` �����R(1125.0m) �` ���J |
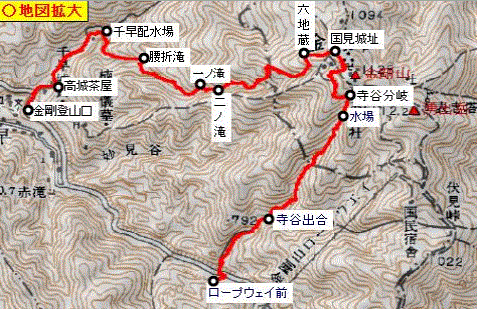
|
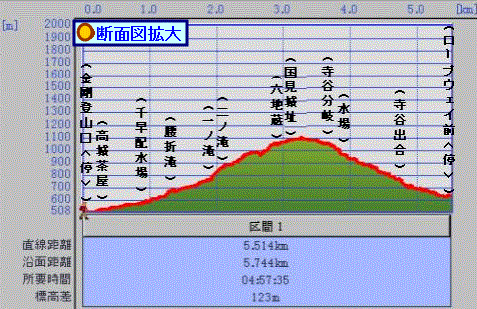
|
| ���u�n�}�v��́�����N���b�N����Ƃ��̈ʒu�̉摜��\�����܂��B | |
| �Q�O�O�U�N�O�V���Q�Q�� �i�y�j���j�����܂�㐰�� �����o�[�F�P�� |
|---|
| ���s�����@�T�D�V�q�^���s���ԁ@�R���ԂS�Q�� �i�x�e���ԁ@�P���ԂP�W���j ���v���ԁ@�T���ԂO�O�� |
|---|
|
�s���|�[�g�摜�t ���N���b�N�ʼn摜���g�債�܂��B |
���� - �o�� | �s���[�g�|�C���g�̂���܂��t |
|---|---|---|

|
10:07 |
�ߓS�������x�c�щw��������o�X�ɏ�p���������o�R���ʼn��Ԃ��邪�A���̏�q�͊F����I�_�̃��[�v�E�F�C�O�܂ŏ���čs�����悤�ō~�肽�͎̂�1�l ���̏�ɔ����g����_�ɍ����̐����M���A�o�X�≡�̃g�C���ŏ������ς܂��U�b�N��2�g�̐������͂����Ă��邱�Ƃ��m���߂ăo�X���������߂� ���܂�̉_�Ԃ������o���v���Ԃ�̑��z�Ƀo�X���͖��邭�Ƃ炵�o����A���݂̋C����26�����w���Ă���̂ō����������Ȃ肻���� |

|
10:10 |
�o�X����200m���߂�ƉE��ɃV�C�^�P���ւ̓����������̂ł������E�܂��邪�A�v�X�ɐ��ꂽ�y�j���Ƃ����̂ɑS���n�C�J�[�̎p����������Ȃ����A�ǂ��������Ƃ��낤�H ����ȋ^��������Ȃ����V�C�^�P���ւ̓����m���r���ƁA�O���Ɍ������`�̋�ԁg���̒J�h�ڎw���đ���i�߂� |

|
10:12 |
�������肩���Y��ɐ������ꂽ�o�R������₩�g�C���̏o�}�����邪�A�g�C���O�̒��ԏ�ɂ�20��߂��}�C�J�[���~�߂��Ă���̂Ŋ��ɑ����̃n�C�J�[�����������ɓo�낤�Ƒ������Ԃɕ�����Ă���̂��낤 �n�C�J�[�̎p����������Ȃ������̂͂��̂��߂������̂��Ǝ����ɔ[�������� |

|
10:14 |
�o�X����X�^�[�g����5�������łs����̕���ɓ˂������� ���ʂ����钃���̍����ł͑��������R���ė���ꂽ�n�C�J�[���C��X�g�b�N�̉���𗎂Ƃ��Ă��� ����͂��̕�������ɑ����ѓ����J���i�ނ��ƂɂȂ邪�A�E�ւ̓��͎R���֍ł��Z�����ԂŒH���瑁�{���� |

|
10:19 | �s���H����5���������Ȋw�������̑O�ɒ����̂ł�������E��ɐL�т�T���Ƃ������т̒��ɐL�т�قڕ��R�Ȓn���ɑ���i�߂� |

|
10:22 |
���т���ƑO���ɍ��̒J���ׂ��R���N���[�g�̋�����̋��������Ă��邪�A���̎�O�ɎԎ~�߂̃Q�[�g������̂ł����ʼnE�ւ̓���`�� ���ւ̗ѓ����J���̓J�g���J�E���̒J�E�킳�ђJ�֑����Ă��� |

|
10:23 | ����7�`80m�ō��肩���瑁�z�����̌��������� |

|
10:26 |
���������ȃR���N���[�g�����}���Ă���� ����n���Ă��s����̂����A���̓V���[�g�J�b�g���Ď�O���E�ւׂ̍����ɑ���i�߂� |

|
10:28 | �������Ȃ̂ő����ɏ[���C��t���Đi�ނƂ����Ճ��[�v�̒���ꂽ20cm���ׂ̍�����ʉ߂��邪�A�����[�g���ŕ��R�ȓ��ɏo�� |

|
���R�ɂȂ����Ƃ���ō�(=�E��)�������̋�����荞�����������Ă��� | |

|
10:29 | �₪�ē��͑��n���ĉE�݉����̎��т�`�����ɂȂ邪�A��̎�O�ʼnE��ɓo���čs�����͐瑁�{�����̂낵����֑����Ă��� |

|
10:34 |
���x���n��Ԃ��Ďb�����̉E�݂�i�ނƒ����������[�g���̌����ȃi����̎��e���}���Ă���� �����ł����ォ��o���Ă���ꂽ�������߂ďo������l�A��̃n�C�J�[�ɓ������� ���z�͍����Ȃ��Ă��������ɑ��̋C����24���Ə����������Ă����悤�� |

|
10:37 |
���e�̍����ɂ͓��������グ��悤�ɁA1m���̍����̊₪�����ɘA�Ȃ��Ă���̂Ŋ������z����ƁA�E�݉����ɋC�����̗ǂ��R�������� �O���������l�A��͉��x��������Ă���R�[�X�Ȃ̂��A�ڐ�Ɏp�������r���[�|�C���g�ɂ������~�܂邱�ƂȂ��ǂ�ǂ��ɐi��ł䂩��� |

|
10:39 - 10:41 | �₪�ĐÂ��ȒJ�ɐ��̗��ꗎ���鉹����ۑ傫���������Ă�����㉺�Q�i�ɗ����鍘�ܑ����L���Ȑ��ʂŌ}���Ă���܂��̂ŁA��ւ̎}����ꉺ�܂ʼn����ă^�b�v���ƃ}�C�i�X�C�I���𗁂т� |

|
10:42 | ���̎R���ɖ߂��đ�̗������������悤�ɋ}�s�Ȋ�������̂œ��݊O���Ȃ��悤�����ɒ��ӂ��č����� |

|
10:42 | ����ɉE���ɑ�̗������������낵�Ȃ���50�p���̌���������荞�ނ��A�H����݂��悤�Ɋۖ��~����Ă���̂Ŋ���Ȃ��悤���ӂ��đ�̏㕔��ʉ߂��� |

|
10:45 |
������ő�҂ɕ�����A���ɐL�т�J�������J�Ȃ̂ł����͉E�ւ̊ۖ؋���n�����c�c�W�I�J�ɑ���i�߂鎖�ɂȂ� �c�c�W�I�J�̓����ɂ�2m����̊�ł���Ԃ̂悤�ɗ����͂������Ă���̂ŁA�┧�ɕt����ꂽ�̂ē�̏�������Ă��̊��o��ƉE�����ɂ͐���K�ꂽ���ܑꂪ�u�₩�Ȑ������������Ă��� |

|
10:46 | �ɂ₩�Ɏ��Ԃ̓���o���čs���ƉE��ɍŏ��̉��炪�����̂ʼnE�ݓ`���ɂ��߂��� |

|
10:50 |
�Ăѕ��R�Ȏ��Ԃ̒���H�邪�y������ł��������̂��A�㕔�����ꂽ�̊��������ǂ��ł���̂��T���Ȃ��悤�ɒʂ蔲���� �w�̐A�ёт���Ƃ���2�Ԗڂ̉��炪�҂��\���Ă���̂ŁA����Ȃ��悤���ӂ��ĉE�݂̊ۑ�����ʂ蔲�� |

|
10:52 | ����3�Ԗڂ̉��炪�����̂ŁA������E�݂��y���������ď��z���� |

|
11:00 | ���̖w�ǂȂ��Ȃ���������݂ɓn���4�Ԗ�(�Ō�)�̉��炪�����̂ō���(=�E)�������Ă܂���֍~��āA�����r�ꂽ���̓���H��Ƃ₪�ăi����̏��ꂪ��������Ėڂ��y���܂��Ă���� |

|
11:02 |
�C���͍X�ɉ�������22�����w���Ă��邪���x���������ׂ����͎��X�ɐ����o���Ă��� 4�Ԗڂ̉��炩��5���A���ܑꂩ��20�����ʼnE��ɐ��ꂪ�����̂ŗ₽�����Ŋ����@���ƌ��錩�銈���҂����C�����ɂȂ� |

|
11:03 | 30m���i�ނƍ���̊┧��`����������������Ȏ��e���}���Ă���� |

|
11:10 | ����ɑ���i�ނ�5�����X���c�c�W�I�̑�(��m��)���p�������Ă����̂ŁA�����ł����������ƃ}�C�i�X�C�I�����^�b�v�����тĐ�ɐi�� |

|
11:11 | �E��(=����)�̋}�Ζʂł͎��т�D���ĖؘR����̃X�|�b�g���C�g���┧���яオ�点�A���グ���ɂ̓X�^�[�g���Ɍ���ꂽ�����_���p�������Ĉ�ʂɐg�����Ă��� |

|
11:17 - 11:20 |
��m�ꂩ��5�����X�ʼnE��������m���̏o�}������̂ŁA����Ȃ��悤�C��t���đ�܂ʼn���^�I���Ŋ��g�̂�@���Ƃق�̏����u�₩�ȗ╗�ƍׂ������𗁂т����Ŋ��͑ނ��Ă��܂� ���݂̋C����20���Ȃ̂ŁA���R�̗����������m��Ȃ������f(^^;) |

|
11:24 |
���̓��܂Ŗ߂���тɍ����|����ƕ��҂��Ă��� �E�ւ̓��͒J������݂ɓn���Đ瑁�{��(�̂낵��)�֑����Ă���悤�����A���͍��ւ̃W�O�U�O�̋}���H�� �����ɕ��������m��̐����␣���ɍ�����q�O���V(�J�i�J�i)��̏����₵���Ȗ������������邪�A�~�J�������錾����Ă��Ȃ��̂ɐ�͊��ɏH�̋C�z�������Ă���̂��� |

|
11:25 | ���т̋}�₪�Ȃ��������ƐA�т��a��ɂȂ����Ƃ���ő傫�ȘI��ɏo�������A����������m��őނ��������܂��N���o��悤�ɐ����o���Ă��� |

|
11:31 - 11:33 |
�U��Ԃ��Ă݂�Ǝ��Ԃ̋}��𒆔N�̒P�ƃn�C�J�[���o���Ă����� �I��ɍ��|���ċx�e�����悤�Ȃ̂ŏꏊ�������Đ�ɐi�ނ��A���������o���Ă��銾�ɃX�^�~�i��D���ĂȂ��Ȃ��s�b�`�͏オ�肻���ɂȂ� |

|
11:43 |
����̘I�₩��10���łs����̕���ɒ��� �Q�l�ɂ����đՂ��������R�o�R���T�C�g�ł́A���������ɂƂ��č����J���[�g�ƍ���������������ƈē�����Ă��邪�A���������������Ă݂����Ȃ��Ĕ����������悤�ɉE�֑���i�߂Č��� |

|
11:46 |
�����ɐ��ʂ̏��Ȃ��Ȃ�����ɏo�邪�A�����E���̊����Ȃ߂�悤�ȗ�������悢��}���z�ɕς���Ă��� �ؗ����Ȃ��̂ŋC�����̗ǂ�����Ɋg�����Ă��邪�A�C������C�ɏ㏸����28�����w���Ă��� ���������̂Ȃ��������������̂ǂ̂��炢�̏����ɂȂ��Ă���̂��ƍl����x�ŗ]�v�Ɋ��������o���Ă��� |

|
11:50 - 11:55 |
�܂��܂����������Ȃ��Ȃ�J���������Ȃ��Ă��邪�؉A���߂��Ă���̂ŁA��̗₽�����ʼnΏƂ����̂���� �C���������܂�23�R���ɉ�����A���錩�錳�C�͉�� |

|
12:17 |
�s����̕���30�����Ńc�c�W�I�J�̌����ɒH�蒅�� ���̌��ԂŃ`�����`�����Ɛ��������������邪�ڂɂ��邱�Ƃ͏o���Ȃ� ����܂ōׂ��Ȃ�������ݐՒ��x�Ɍ����Ă�����������Ȃ��Ȃ�A100m���O���ɂ͗Ő��������o�����ڂ̑O�̎G�����E���Ղ��đ���������߂邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ� |

|
12:15 | ���u���������s���Ă܂ŗŐ��ɏo����̋������Ȃ��̂ŁA���̊�ǂɗ���Ȃ��ɕt����ꂽ�̓�ɗU������Ċ�ǂ��悶�o�鎖�ɂ��� |

|
12:33 | ��ǂ̏�ɂ̓T�T�����g��������ȓ��ݐՂ��k�ɐL�тĂ���̂œ��ݐՂ�H���Ă݂� |

|
12:34 | �����ɃT�T�����r���ƕ��R�ȕ�n���̑�n�ɔ�яo���̂� |

|
12:36 | ��n��ʂ�߂���ƌ��o���̂��鍂���J�R�[�X�ɍ������� |

|
�����E������Z�̂̒n���̏o�}�����ĕ��R�ȎR�����ւ̓���H��� | |

|
12:39 | 2�`3���Ő�(������)���[�g�ɍ�������̂ł����ł��E�i�ނ� |

|
12:41 |
�ق�̏����Ŗڂ̑O���傫���g����ƍs�ғ��Ղ̈�˂�����L��ɓo��t�� �؉A��I��ő����̃n�C�J�[�����H�^�C�����v���v���Ɋy����ł����邪�A�H���͂����̏ꏊ�Őۂ邱�Ƃɂ��Ă���̂ł����͍���ɐi�� |

|
12:45 | ��ˉ��̊K�i��`�����ƓW�]�̗ǂ������隬�L��ɒ������A�ɂ��Ă��邽�ߒ��]�͂��܂���҂ł��Ȃ��̂ʼnE���̊K�i����]�@�֎����̍���ɑ����ۖ؊K�i��o��� |

|
13:48 - 13:55 |
���̎��тɈ͂܂ꂽ�����22���Ɖ��K�ȋC�������A���������ނ��̂�҂��Ēx�����H�^�C���Ƃ��� �K�������̃x���`���Ă���̂ŃU�b�N�����낵�Ď����̈ꎞ�ɐZ�� �������T�̑��Ԃ��H���x�߂Ă����A�T�M�}�_���������������ɒ��H���y����ł���悤�� |

|
13:57 | �H��̈ꎞ���ςނƗ�ɂ�����]�@�֎��̑O��ʂ蔲���ĎR�������������Â��ȗV�������m���r���H�� |

|
14:05 | ���؉Ƃ̕揊�O��������≮�O��ʂ��ċC�����̗ǂ��ɂ₩�ȋN���̗V������H��ƁA5�����ʼnE�����������R�[�X���ڂɕt�� |

|
14:15 | �X��5�����œ��W�͂Ȃ������J�R�[�X���E��ɉ����čs���̂ł��������邱�Ƃɂ��� |

|
14:16 | �A�т̒������r�ꂽ��������D���ĉ����Ă䂭�ƁA�₪�ĉE�肩�當������R�[�X����̍L�������������Ă��� |

|
14:23 | ������5m������ƁA�㕔����ג����p�C�v�ɓ����ꂽ�͂��Ȑ������ꗎ���鐅�ꂪ���� |

|
14:31 |
�b���}�ȒJ��H�邪�A����10�����ł��L�����R�n�ɒ��� �Ăы}�ŏ����r�ꂽ�J���肪�n�܂邪�A���{���|�������ǂ��E����ʂ蔲���� ����͎G�Ɉ͂܂�Ă���̂Ŏv���̂ق����邢�J����`�����ɂȂ邪�A���̒J�ŏ��߂Ẵn�C�J�[�Ƃ���Ⴄ �u����ɂ���v�A�u���C��t���āv �y�����A�����킷���A���܂݂�̎��Ƃ͑ΏƓI�ɖw�NJ����������Ɍy�₩�ȑ����ň������o���čs�������p�������� |

|
14:41 | �Ԃ��Ȃ����R�ȐA�ёт̒����ׂ����͊ɂ₩�ɉ����čs���ƁA�E��Ƀ|�b�J���Ǝ��т��r��Ďx�J�𗬂ꗎ����₽�������q�������Ƃ����╗�Ō������Ă���� |

|
14:44 | �₪�Đ��̗�������`���A���݂ɓn��Ƃ��������͏����ȑ�ɂȂ��Ă���̂ō���(=����)�̊�`���Ɍ����~��� |

|
14:47 | �ꉺ�ő���E�݂ɓn��Ԃ��ƁA���͍����ꗎ�����ׂ��������ɕς�葫���ɂ͖̍����I�o���Ă���̂��T���Ȃ��悤�`������ƁA�����ł�������R����������P�ƍs�̏����Ƃ���Ⴄ |

|
14:53 |
�����E��̎x�J����₽��������ǂ�`�������Ă��� �����ł��^�I����Z���Ď����@���Đ��C�����߂��A��������������悤�ɂ��čŌ�̍������ �����œ��͋����Ȃ�A���������������悤�ȐS�ׂ���������������悤�Ɍ������� |

|
14:55 | �E��Ɍ��グ�Ă�������������Ɍ���悤�ɐ܂�Ԃ��ƁA���J�ւ̕�������40���ł����ڂ̉���ʂ��ܑ����ꂽ�ה��J�ɍ~�藧�� |

|
15:00 |
�������E��5m�����������œ��̉E��ɐ���������ƁA�����ʼnE������ꒆ�����R�[�X�������邪�A��͖ʔ��݂̂Ȃ��}�ȕܑ����H���Ђ����牺�鎖�ɂȂ�A���̎��ԂɂȂ��Ă�������R����ڎw���n�C�J�[�Ƃ���Ⴄ �O�������ɂ͕���������E���U���Ƃ���ܑ����H�������Ă���ꂽ�n�C�J�[���U�����鎖���o���邪�A��͂�l�C�̂���R�ł��邱�Ƃ��M���� |

|
15:05 | 5���ōה��J���~�肫���ă��[�v�E�F�C�O�̃o�X���ɔ�яo�� |

|
15:07 | �o�X�҂��̎��Ԃ𗘗p���ăg�C���O�̐�������ď㔼�g��@���ĊȒP�Ȓ��ւ����ς܂��A15��25���̓�C�o�X�ɏ�荞�ݍ������܂������ɎR�ɗV��ŖႤ���Ƃ��o�����[�����𖡂킢�Ȃ���͓�����o�R�Ŏ���Ɍ����� |